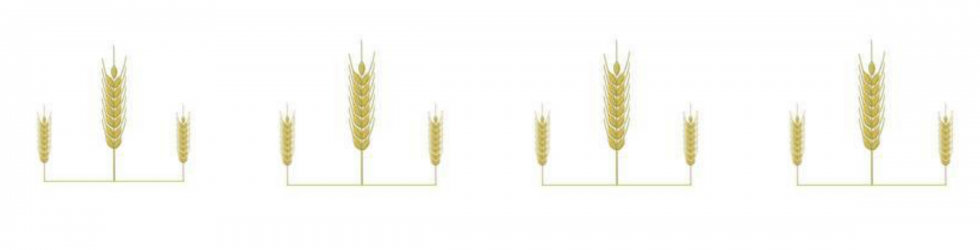DevLOVE関西 現場甲子園2015 「西日本大会」に行ってきました
DevLOVE関西 現場甲子園2015 「西日本大会」に行ってきました。
全部で15セッション。全部現場の話。
3セッションが同時進行するスタイル。
他社さんの現場がどうなのか知る機会って本当に少ないと思います。
貴重な勉強会でした。
気になったキーワードと感想を書いています。
目次
オープニング
中村 洋さん
- 開発の楽しさを広げよう
- 現場の前進、循環に役立てる
主意
- 話し手は現場の実践者
- 聞いた現場の話から自分の現場とのDiffを自分の現場に活かす
- 現場は知識と経験の集積場
http://bit.ly/1NxGlr2
3会場で3セッションが同時進行するスタイルでした。
以下は自分が参加したセッションです。
ウォーターフォール開発でも変化を抱擁するために行ってきた悪戦苦闘日記
川辺 卓矢さん
- PMBOK-PMが考えるべき9つの知識領域
- ざっくり見積もりは本金額になる
- システム部門担当者に当事者意識がない
- 暗黙知的な要求取りこぼしが後々のリスクになる
- ユーザ部門と会えない
- 開発スケジュールはCCPMを参考にしている
- MVCでViewはころころ変わってもModel,Controllerは変えないというのもリスクヘッジ
- サンプルデータにはリアリティをもたせる
感想
開発後期に入ってからの突然の仕様変更に対して、リスクをどう許容するかのお話しでした。
今の立場で内製開発を行う上でのリスクヘッジをしなくても取り戻せはしますが、時間的なトータルコストや信頼関係には影響しますね。
なるほどでした。
後は「同じバスに乗る」考え方で見ると外製開発の際に発注側としてもリスクをヘッジしておく事で、
プロジェクト全体の効率を上げる事につなげたいと思いました。
Misocaチームの自己組織化への取り組み
小久保 祐介さん
- 読んだ本の共有、コードレビューで気になった箇所の共有、技術的な話でコミュニケーション
- 朝会で日報を見る。毎日30分。
- フリカエリは毎週水曜日。Trelloのラベルをうまく使う。
- プロダクトの作り方をふりかえる
感想
自分の現場の今のやり方は、朝会は毎朝壁の付箋で予定とポエムで5分、フリカエリは毎日予定に対した結果ベースでボードにKPT書いてるのですが、
フリカエリの際にタスク単位で予定どおりかどうかぐらいに意識がいっているので、そうではなく、サービスの作り方をフリカエらないとなーと思いました。
そして前のセッションとも関係してくるのですが、ベストプラクティスな作り方が出来るようにプランニングにつなげていかないとなーって思いました。
あと、世間話もいいのですが、技術的な雑談を継続的にやってみようと思いました。
メンバーの成長を促進する組織マネジメント
細谷 泰夫さん
- 1~2年目社員がソフトウェア内製を普通の納期でやらなければならない
- 成長するのは本人次第、最初の一歩を踏み出す支援は出来る
- その経験が事業に貢献する人材として必要だからやる
- 自分たちのアイデアを活かして成果を得る経験を積んで達成したことによる成長を実感して歩み始める事が出来る
- 頻繁な繰り返しプロセスとフィードバック
- Fearless Journey ワークショップの結果を個人目標に入れる
- スコープを小さくして結果を素早く出して改善する
- スコープが小さいと手段のボリューム、複雑性も小さくなる
- 「収集」ターゲットを絞らない、「調査」ターゲットを絞る
感想
規模はもちろん違いますが、同じような境遇ではあると思いました。
技術職なので本人(の勉強)次第ではあるのですが、「最初の一歩を踏み出す支援は出来るはず」というお話しでした。
確かに。そのとおり。
ですが、いかんせん自分の支援が足りていないのが現状で課題は多くあるなと思いました。
スコープを小さくして反復を定義して計画と実行を繰り返して課題と手段をマッチングさせる。
難しいですな〜。がんばろう。
ただ、達成したことによる成長を実感してもらうと状態にする事はすぐにでも、というかもっともっと出来ると思うのでやってみよう。
失敗しても経験としては絶対にありだと思う。
フォローも含めた支援は全力であたろう。
今度はそれが自分の経験にもなる。
越境する/しない現場のDiff
中村 洋さん
- 経営者にあなたが問題の中枢だと言う事もある
- 動きの早いビジネス環境では定められた枠の中で動いているだけでは生き残れない
- 自分でハンドルを握れるようにする
- 上司がやれと言ったからやっていると言うのは格好悪い
- インセプションデッキ
- ドラッカーエクササイズ-期待を擦り合わせて自分ごとになっていく
- うまくいかない事と向き合える。うまくいかなかった事から何を学ぶか?
- すべて1人でやる必要はない
感想
「経営者にあなたが問題の中枢だと言う事もある」は本当にすごい。
でも、「誰が正しい」ではなく「何が正しい」で考えると当たり前に必要な事なんだと思います。
越境の必要性として仰っていた「自分でハンドルを握れるようにする」については確かにこの方が腹落ちして仕事できると思いました。
「インセプションデッキ」「ドラッカーエクササイズ」は知らなかったです。勉強不足です。というか無知です。でも、やってみたいです。聞けてよかったです。
やるからにはこういった事を自分で腹落ちしてメンバーに説明できないと。「現場コーチをやってる人が言ってた」からではダメだと思いました。
サービス×現場
牛島 真一さん
- マネージャ集中型から、それぞれのチームで考えながら計画するようになった
- 新しい事に挑戦して欲しいので、自分自身のinput/outputを増やしていく
- グループ長同士でタスクボードを作って朝会、フリカエリをする
感想
うちの現場では粒度の細かいタスクはRedmineで、粒度の大きなタスクはボードにして他部門から一目で見えるようにしています。
部門間での認識共有に意味があると思ってやっているのですが、その裏付けにも、今日聞いた事例が非常に参考になりました。
他部門が何をどれぐらいの状態でやっている、やろうとしているのか、を知る事は必須だとは思いますが、
そのためにお互いの時間を拘束するべきか、というとそうでもなくて、非同期にやれるのが1番いいのかな〜って思います。
でもこれだとやる部門、やらない部門に差はできそうかなとは思いました。
あと、勉強会に行ったり新しい事に挑戦するようになったメンバーが実は隣で司会をしていた!というのが本当に素晴らしい!と思いました。
質問して良かった。
エンジニアが幸せな人生を過ごすための学び方、関わり方、あり方
久保 明さん
- 読書は質を高めて量を増やす、両方大事
- 出来るだけ源流を読む、優秀な人のおすすめ書籍を読む
- 一度だけ全部読む、重要なところだけ何度も読む
- 勉強会は知識の確認、仲間を見つける、いつからでも始められる
- Jenkinsでビルド、テスト、ドキュメント、解析を自動化
- 定形業務は自動化する
- チームに伝えるのも発表、チームとして成長すれば幸せ
- 行動科学マネジメント、いつでもどこでも誰でも出来る再現性のあるマネジメント
- 結果の差は行動の差
- 出来ない理由は、やり方がわからない、続け方がわからない
- OJTという名の放置プレイ、川に突き落として泳げというようなもの、スイミングスクールは段階的に教えるからみんな泳げる
- 行動の差→文書化→説明 MORS
- PST 即時は60秒以内
感想
読書、勉強会、実践、発表についてどう関わってこられたかを生々しく面白く発表されていました。
今日の発表そのものが実践であり発表なんですよね。
体現されていると思いました。
「前提が違うとやれる事は全然違う」はまったくもってそのとおりだと思います。
「前提」=「あきらめ要因」であれば出来る事さえ遠のいていくと思います。
一緒に働くという事は人の人生を預かっているという事、影響を与えるという事を改めて強く思いました。
全体を通じて
まずは今日感じた事を現場で雑談したいと思います。
そしてやってみたいと思った取り組みを、押し付けではなく現場で試してやってみる空気に自然になるように、
今日教えてもらった事に対して自分が感じたように、自分で腹落ちした言葉でWhyから説明出来るように、
今日のヒントをもう一歩深堀したいと思いました。
最後までお読みいただきましてありがとうございました!
「AWS認定資格試験テキスト&問題集 AWS認定ソリューションアーキテクト - プロフェッショナル 改訂第2版」という本を書きました。
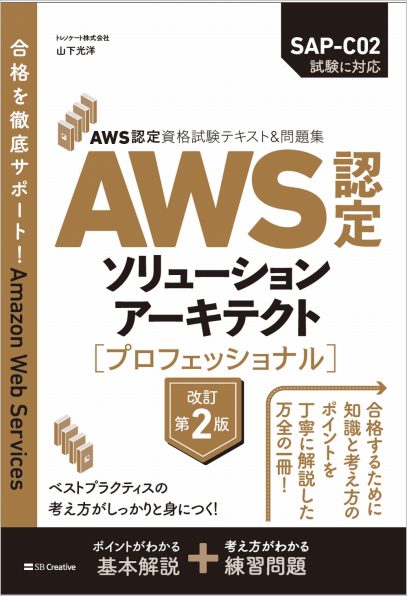
「AWS認定資格試験テキスト AWS認定クラウドプラクティショナー 改訂第3版」という本を書きました。
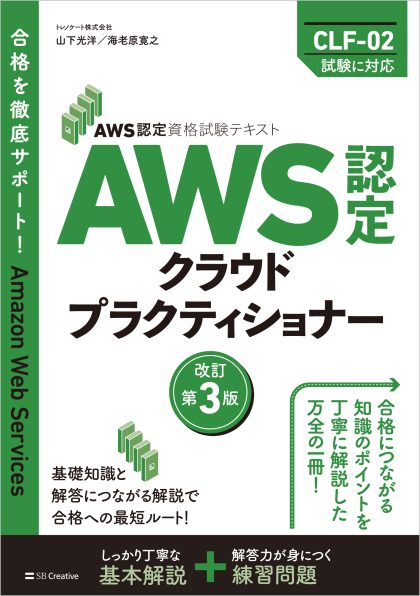
「AWS認定資格試験テキスト AWS認定AIプラクティショナー」という本を書きました。
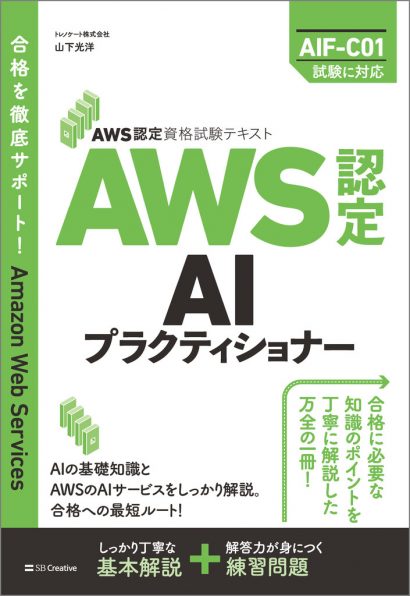
「ポケットスタディ AWS認定 デベロッパーアソシエイト [DVA-C02対応] 」という本を書きました。

「要点整理から攻略するAWS認定ソリューションアーキテクト-アソシエイト」という本を書きました。
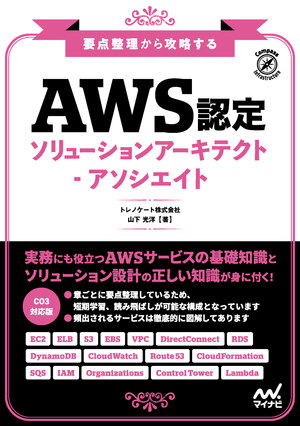
「AWSではじめるLinux入門ガイド」という本を書きました。
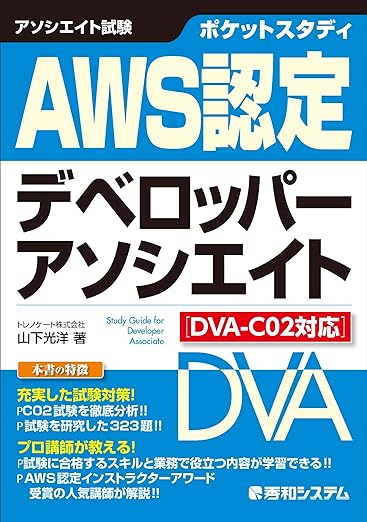
開発ベンダー5年、ユーザ企業システム部門通算9年、ITインストラクター5年目でプロトタイプビルダーもやりだしたSoftware Engineerです。
質問はコメントかSNSなどからお気軽にどうぞ。
出来る限りなるべく答えます。
このブログの内容/発言の一切は個人の見解であり、所属する組織とは関係ありません。
このブログは経験したことなどの共有を目的としており、手順や結果などを保証するものではありません。
ご参考にされる際は、読者様自身のご判断にてご対応をお願いいたします。
また、勉強会やイベントのレポートは自分が気になったことをメモしたり、聞いて思ったことを書いていますので、登壇者の意見や発表内容ではありません。
関連記事
-

-
実録 JAWS DAYS 2017 ~RoadTrip,スタッフ,ハンズオンメンターで参加しまして~
今年もJAWS DAYSにいってまいりました。 RoadTripの話 去年に引き …
-

-
Java SE 7 Silver対策勉強をしながらメモ 2015/2/5
本日は例外。 いつものごとくマークダウンで記載したのでそのままJetpack M …
-

-
交通情報系スキルを事例に見る日常生活に溶け込むスキルのテクニック(Alexa Day 2019でのブログ)
以下は、気になったことのメモとか感想を書いています。 登壇者、発表者、主催企業な …
-

-
ヤマムギvol.13 AWSアカウント作成と保護のデモをしました
2021年のゴールデンウィークチャレンジということで、10日連続で毎朝30分デモ …
-

-
「IoT縛りの勉強会/SIer主催版 SIerIoTLT vol4」に行ってきました
「IoT縛りの勉強会/SIer主催版 SIerIoTLT vol4」に行ってきま …
-

-
「CLS高知2023戻り鰹編」に参加しました
12回目のCLS高知、2023戻り鰹編に参加しました。 高知駅付近から弁天座へ自 …
-

-
「IBM Cloud Community Summit 2018 フルマネージドデータベースというのは使えるのか?IBM Cloudでのデータ活用事例いろいろ」でIBm Cloudのデータベースサービスを聞かせていただいた
IBM Cloud Community Summit 2018におじゃましました …
-

-
Alexa Day 2018で「How do we connect VUI to the real services using serverless」を聞きました
photo by Atsushi Ando Serverless for VUI …
-

-
「SIerIoTLT vol9@サポーターズ 」でLTしました〜
サポーターズさんで開催されたSIerIoTLT vol9でLTしてきました。 今 …
-

-
Alexaで作る受付システム(Alexa Day 2019でのブログ)
ランチタイムセッション3本目はウフルさん。 たくさんのLEDをコントロールされて …